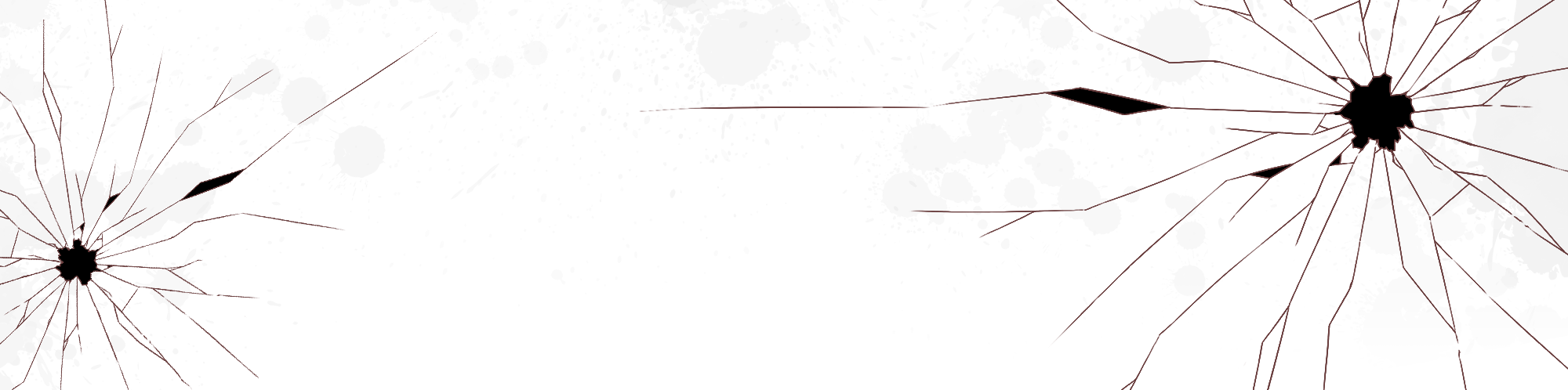第九話 薬物反応
3人は荒野で見つけたモーテルで束の間の平和な生活を送っていた。
宿泊費も安く、車を出せば町までのアクセスも問題ない。しばらくここに滞在してもいいか……などと、気楽な時間を過ごしていた。
その間はファティマの男性恐怖症克服プログラムを継続している。半歩ずつ距離を縮めてゆき、二週間も滞在するころにはほぼゼロ距離まで近づくことが可能になっていた。
「この距離でも大丈夫なのお前?」
「相当我慢してるからね?!でも、まあ、耐えられないこともないかなって……。でも基本的にあんまり近づいてほしくないからね?!」
ヴィクトールとエンリーケはファティマに近づいても逃げられなくなったことに驚いていた。おそらく相当な葛藤や忍耐や精神力を使って努力しているのだろうが、それにしてもこの至近距離でも発狂しなくなったのは大きな進歩だ。
「早く離れて!私耐えたでしょ!もう今日はおしまい!」
「あ、ああ。解った。頑張ったな。お疲れさん」
ファティマはすぐに縄張りであるソファーの上に帰ってしまったが、初日のように鉄砲玉のような勢いで飛び乗ったりはしない。自然な動きでソファーに体を預ける。落ち着いたものだ。
「じゃあファティマ。次は何を練習しような?距離はクリアしたから、触っても平気になるよう訓練するか?」
ヴィクトールの提案に、ファティマは悲鳴のような抗議の声を上げた。
「えええええええ?!触ってくるの?もういいじゃん!距離我慢したんだから!」
エンリーケが厳しく指摘する。
「元々は触ったら吐いたから練習するようになったんだろ。触っても平気になってもらわないと合格したとは認められないぜ」
ファティマは盛大なため息を吐いて、「解った……。頑張る う……」と不承不承了解した。
その夜、三人はファティマが距離の問題をクリアしたことを祝して、バーで飲もうと夜の街に繰り出した。
外食をすることは未だファティマにとって警戒心が働く行動だ。買い食いのように薬を仕込む余裕もなく食事できるほうがよほど安心できる。現在では二人の男が調理した食事は信頼して食すことができるようになったが、外食は何が入っているか判らず、未だ信用できない。アルコールなどもってのほかだ。
「えー、ファティマ、相変わらずその試験紙持ち歩くのかよ。信頼してくれよー」
「あんたたちばかりを警戒してるわけじゃないわ。どこに敵がいるかわからないでしょ?」
「酒場のマスターが仕込むの?んなわけないだろ。そんなことする店主の店なんか安心して通えねーよ」
エンリーケは鼻で笑ったが、ファティマは警戒心が解けない。男二人のことは信頼しているが、変な犯罪者に誘拐されるかもしれないではないか。まして組織から命を狙われているのだ。用心するに越したことはない。
「考えすぎだって。ほんとに用心深いなファティマは」
一笑に付したヴィクトールだったが、彼はなぜか第六感がファティマの指摘を捨てようとしてリサイクルし、頭の隅で不安を煽っているのを感じていた。
宿泊費も安く、車を出せば町までのアクセスも問題ない。しばらくここに滞在してもいいか……などと、気楽な時間を過ごしていた。
その間はファティマの男性恐怖症克服プログラムを継続している。半歩ずつ距離を縮めてゆき、二週間も滞在するころにはほぼゼロ距離まで近づくことが可能になっていた。
「この距離でも大丈夫なのお前?」
「相当我慢してるからね?!でも、まあ、耐えられないこともないかなって……。でも基本的にあんまり近づいてほしくないからね?!」
ヴィクトールとエンリーケはファティマに近づいても逃げられなくなったことに驚いていた。おそらく相当な葛藤や忍耐や精神力を使って努力しているのだろうが、それにしてもこの至近距離でも発狂しなくなったのは大きな進歩だ。
「早く離れて!私耐えたでしょ!もう今日はおしまい!」
「あ、ああ。解った。頑張ったな。お疲れさん」
ファティマはすぐに縄張りであるソファーの上に帰ってしまったが、初日のように鉄砲玉のような勢いで飛び乗ったりはしない。自然な動きでソファーに体を預ける。落ち着いたものだ。
「じゃあファティマ。次は何を練習しような?距離はクリアしたから、触っても平気になるよう訓練するか?」
ヴィクトールの提案に、ファティマは悲鳴のような抗議の声を上げた。
「えええええええ?!触ってくるの?もういいじゃん!距離我慢したんだから!」
エンリーケが厳しく指摘する。
「元々は触ったら吐いたから練習するようになったんだろ。触っても平気になってもらわないと合格したとは認められないぜ」
ファティマは盛大なため息を吐いて、「解った……。
その夜、三人はファティマが距離の問題をクリアしたことを祝して、バーで飲もうと夜の街に繰り出した。
外食をすることは未だファティマにとって警戒心が働く行動だ。買い食いのように薬を仕込む余裕もなく食事できるほうがよほど安心できる。現在では二人の男が調理した食事は信頼して食すことができるようになったが、外食は何が入っているか判らず、未だ信用できない。アルコールなどもってのほかだ。
「えー、ファティマ、相変わらずその試験紙持ち歩くのかよ。信頼してくれよー」
「あんたたちばかりを警戒してるわけじゃないわ。どこに敵がいるかわからないでしょ?」
「酒場のマスターが仕込むの?んなわけないだろ。そんなことする店主の店なんか安心して通えねーよ」
エンリーケは鼻で笑ったが、ファティマは警戒心が解けない。男二人のことは信頼しているが、変な犯罪者に誘拐されるかもしれないではないか。まして組織から命を狙われているのだ。用心するに越したことはない。
「考えすぎだって。ほんとに用心深いなファティマは」
一笑に付したヴィクトールだったが、彼はなぜか第六感がファティマの指摘を捨てようとしてリサイクルし、頭の隅で不安を煽っているのを感じていた。