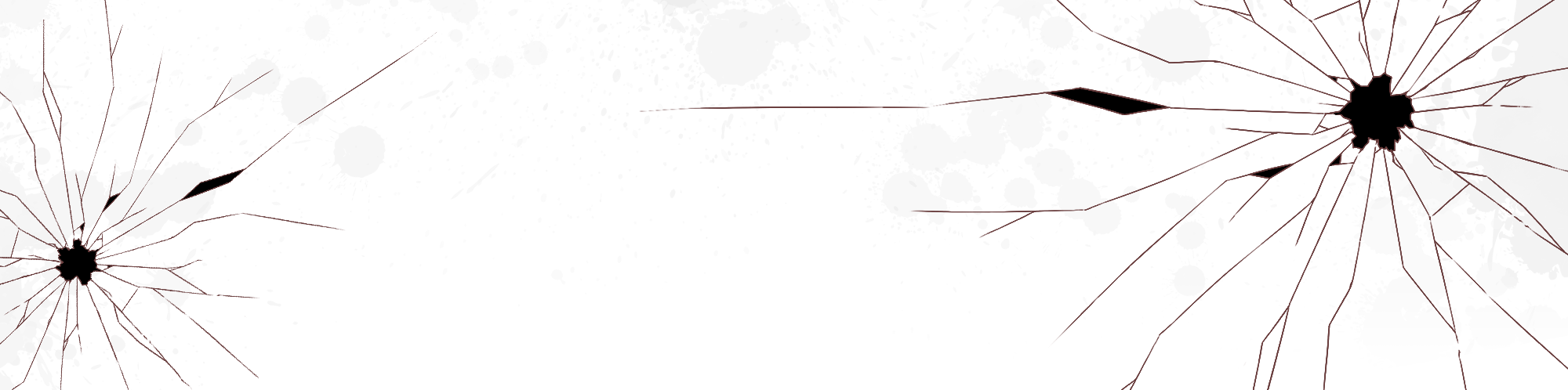第六話 男性恐怖症
あたしの父はセレンティア総合病院の院長。そして医師会の会長よ。みんなが父に逆らえない、医者の世界のトップ。
でもそれは表の顔。本当はペドフィリアで子供のいやらしい写真をコレクションするような変態なの。勿論私も子供の頃に父から犯されたわ。その時に私が抵抗できないように、ドラッグを盛って、黙らせて犯したの。
あたしは辛くて嫌でたまらなかったけど、抵抗する力が出せなかった。それから食事にも変な薬を盛られていたみたいでね。体の成長が止まる薬品を盛られていたみたい。そのせいであたしは胸も小さいまま、体も子供っぽくて低身長になったのよ。
あたしは父の薬物悪用が許せなかった。だから独学で薬について調べた。そして、一刻も早く薬剤師になって、ドラッグが悪用されないように研究者になりたかったの。
そこで編み出したのがあの検査シート。あたしはレイプドラッグや毒物が食事に混ぜられて、レイプされることをこの世で一番恐れてる。だから男はみんな敵だと思ってるし、生理的に受け付けない。婚約者もあんなのただのエロ猿だし、あんたたちもどうせあたしを乱暴しようと思ってるんだろうなって疑ってるわよ。
衝撃の告白だった。実の父親に薬を盛られて犯され、身の回りの人間はだれも信用できない人生。薬のせいで成長も止められたとなると、彼女が天才薬剤師になるためには相当な執念と努力があったに違いない。ヴィクトールとエンリーケはしばらく黙っていたが、絞り出すようにヴィクトールが沈黙を破った。
「た……大変だったんだな……。でも、安心しろよ。俺達はそんな薬物知らねーし、お前に毒盛るつもりもないし、それ以前に毒も薬も持ってねーから……。とりあえず、俺たちの作る飯は安心して食えよ」
ファティマは席に座ると、「昔のこと思い出して食欲無くなっちゃったわ」といって、ミニトマトをつついた。
その後もファティマはヴィクトールとエンリーケとは一定の距離を保って近づこうとしなかった。ベッドは汚らしいと言って寝ようとせず、ソファーで眠った。さらにソファーのそばには包丁を置き、寝込みを襲われないよう警戒していた。ヴィクトールとエンリーケはガードが堅いというレベルではないほど警戒するファティマに手を焼いていた。
「確かに……こんな生き方してたら死んだほうがマシだろうなあ」
「殺してあげたほうがいいのかな……?でも、なんか同情しちゃって殺しにくくなったな」
一カ月ほど生活を共にすると、ソーシャルディスタンスの距離に変化はないものの、だいぶ親しくコミュニケーションが取れるようになり、一見打ち解けたように見えた。しかし、再びヴィクトールのスマートフォンに、組織から連絡が入った。
でもそれは表の顔。本当はペドフィリアで子供のいやらしい写真をコレクションするような変態なの。勿論私も子供の頃に父から犯されたわ。その時に私が抵抗できないように、ドラッグを盛って、黙らせて犯したの。
あたしは辛くて嫌でたまらなかったけど、抵抗する力が出せなかった。それから食事にも変な薬を盛られていたみたいでね。体の成長が止まる薬品を盛られていたみたい。そのせいであたしは胸も小さいまま、体も子供っぽくて低身長になったのよ。
あたしは父の薬物悪用が許せなかった。だから独学で薬について調べた。そして、一刻も早く薬剤師になって、ドラッグが悪用されないように研究者になりたかったの。
そこで編み出したのがあの検査シート。あたしはレイプドラッグや毒物が食事に混ぜられて、レイプされることをこの世で一番恐れてる。だから男はみんな敵だと思ってるし、生理的に受け付けない。婚約者もあんなのただのエロ猿だし、あんたたちもどうせあたしを乱暴しようと思ってるんだろうなって疑ってるわよ。
衝撃の告白だった。実の父親に薬を盛られて犯され、身の回りの人間はだれも信用できない人生。薬のせいで成長も止められたとなると、彼女が天才薬剤師になるためには相当な執念と努力があったに違いない。ヴィクトールとエンリーケはしばらく黙っていたが、絞り出すようにヴィクトールが沈黙を破った。
「た……大変だったんだな……。でも、安心しろよ。俺達はそんな薬物知らねーし、お前に毒盛るつもりもないし、それ以前に毒も薬も持ってねーから……。とりあえず、俺たちの作る飯は安心して食えよ」
ファティマは席に座ると、「昔のこと思い出して食欲無くなっちゃったわ」といって、ミニトマトをつついた。
その後もファティマはヴィクトールとエンリーケとは一定の距離を保って近づこうとしなかった。ベッドは汚らしいと言って寝ようとせず、ソファーで眠った。さらにソファーのそばには包丁を置き、寝込みを襲われないよう警戒していた。ヴィクトールとエンリーケはガードが堅いというレベルではないほど警戒するファティマに手を焼いていた。
「確かに……こんな生き方してたら死んだほうがマシだろうなあ」
「殺してあげたほうがいいのかな……?でも、なんか同情しちゃって殺しにくくなったな」
一カ月ほど生活を共にすると、ソーシャルディスタンスの距離に変化はないものの、だいぶ親しくコミュニケーションが取れるようになり、一見打ち解けたように見えた。しかし、再びヴィクトールのスマートフォンに、組織から連絡が入った。