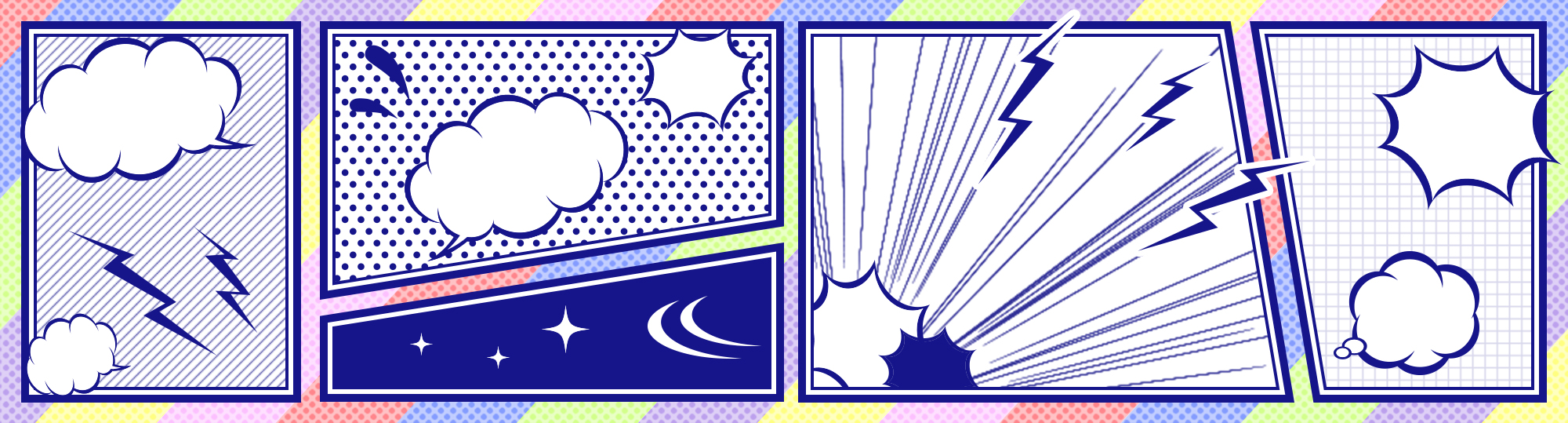風邪を引いたカレカノ
まもうさ
※衛大学四年、うさぎ短大一年
『ピンポーン』
まもちゃんのお部屋の前に着いた私はうきうきとインターホンを鳴らした。
…あれ?
『ピンポーン』
いつもならわりとすぐに返事をしてくれるはずの大好きな声が聞こえなくてもう一度押す。
…お留守かな?
今日まもちゃんちに遊びに行くことは特に言ってなかった。でも大抵土曜日はお邪魔しに来てるから大丈夫かなと思ったんだけど…
スーパーで買ってきたお昼ご飯の材料に目を落としてちょっとだけ溜め息。
けれどすぐに気を取り直してショルダーバッグから合鍵を取り出す。
「えへへっこれはもう彼女というよりは通い妻ってやつよねー!もうやっだーっうさぎちゃんたら気が早いー♪♪お邪魔します!!」
鍵を捻りながら独りで一気にそこまで言って開けると、リビングに続く廊下の中央。ちょうどまもちゃんの部屋の前にその彼がパジャマ姿で倒れているのを目にして買い物袋がドサリと落ちた。
「ま…まもちゃんっ!!」
一気に傍まで駆け寄って体を揺する。
すごく熱い…っ息も苦しそう。どうしよう…っ
「しっかりしてまもちゃん!」
「う……さ……?」
「まもちゃん!大丈夫!?」
「ああ……ただの、風邪だから…」
そう言いながらゆっくり起き上がるまもちゃん。私はそれを支えてベッドまで一緒に向かった。
とりあえずお布団をしっかり掛けてあげて、冷蔵庫にあったミネラルウォーターを飲んでもらった後、氷水でしぼったタオルをおでこに乗せてあげると一息付いた。
「ありがとな。」
「どういたしまして。けど、廊下で倒れちゃうくらいなのにただの風邪だーなんて!我慢しちゃだめだよ!ほんっとーーーにっびっくりしたんだから!お医者様には行ったの?」
「…行ってない。」
「じゃあ今からは…あ!土曜日だから午後はお休みかぁ…でもうちのかかりつけのお医者様なら連絡すればすぐに診てもらえるよ!?」
「大丈夫。市販の薬の残りもあるし。俺の見立てでは熱さえ下がれば問題ないよ…」
そんな弱々しく微笑まれて言われても全然安心できないよ…っ
「それに、うさが来てくれたし。付き合い始めのころに風邪引いたときは、正直お前の有り余る善意で殺されると思ったけど…」
「むう!弱ってても意地悪言ってー!」
「いや、はは…だけど今はずいぶんしっかり奥さんしてくれてるからな…」
「お、おくさん…///」
そんなっ嬉しそうにそんな事言われたら、私も熱が出そうだよ…っっ
「悪い、まだそんなんじゃないのにな…弱ってると変なこと言っちまうな、俺…」
「変じゃない!だって私、今からいろいろ練習しておくんだもんっ!まもちゃんの自慢の奥さんになれるように。」
「かわいいこと、言ってくれるんだな…」
すっと、右手が私の頬に触れて、そのいつもより高い温度のそれに頬から耳を撫でられるとバクンと心臓が跳ね上がる。
「ねえ奥さん、甘えて、いい?」
「…!!」
私をじっと見つめるその瞳はとろりと甘くて目が離せない。
「まもちゃ…」
そんな中、測ってた体温計のアラームが鳴った。
慌てたように右手を離してそれを見たまもちゃんは、真っ赤な顔のまま貸してと言う私になかなか渡してくれない。
「も、もーまもちゃん!見せて!」
「…見ても、驚くなよ…?」
そう言って熱で(?)真っ赤な顔したまもちゃんが拗ねた様子で渡してくる。
それはさっきの雰囲気とはがらりと違って子供みたいで。風邪を引いたまもちゃんは私の心臓を何度も跳ねさせる。
「って、39.9℃ーーーー!!??」
「く…っうさ…頭に響、く…」
「あ、ごめん。って、私タオル代えてくるっ!お布団ももう一枚出してくるからねっっ!!」
「うさたのむ いまはおおごえ やめてくれ」
一瞬の甘い空気も吹っ飛んで、うわごとみたいなことを言ってるまもちゃんを残して私は部屋を猛ダッシュで出て行った。
ひいいいいっ風邪引いたまもちゃん心臓に悪い!早く良くなってもらわなきゃ…うさぎちゃんの頭が溶けちゃうからーーーー!!
さっきの言葉と掠れた声。触れられた頬と耳。その体温。それを思い出した私は鳴り止まないドキドキを胸に、心の中で叫んだ。
※衛大学四年、うさぎ短大一年
『ピンポーン』
まもちゃんのお部屋の前に着いた私はうきうきとインターホンを鳴らした。
…あれ?
『ピンポーン』
いつもならわりとすぐに返事をしてくれるはずの大好きな声が聞こえなくてもう一度押す。
…お留守かな?
今日まもちゃんちに遊びに行くことは特に言ってなかった。でも大抵土曜日はお邪魔しに来てるから大丈夫かなと思ったんだけど…
スーパーで買ってきたお昼ご飯の材料に目を落としてちょっとだけ溜め息。
けれどすぐに気を取り直してショルダーバッグから合鍵を取り出す。
「えへへっこれはもう彼女というよりは通い妻ってやつよねー!もうやっだーっうさぎちゃんたら気が早いー♪♪お邪魔します!!」
鍵を捻りながら独りで一気にそこまで言って開けると、リビングに続く廊下の中央。ちょうどまもちゃんの部屋の前にその彼がパジャマ姿で倒れているのを目にして買い物袋がドサリと落ちた。
「ま…まもちゃんっ!!」
一気に傍まで駆け寄って体を揺する。
すごく熱い…っ息も苦しそう。どうしよう…っ
「しっかりしてまもちゃん!」
「う……さ……?」
「まもちゃん!大丈夫!?」
「ああ……ただの、風邪だから…」
そう言いながらゆっくり起き上がるまもちゃん。私はそれを支えてベッドまで一緒に向かった。
とりあえずお布団をしっかり掛けてあげて、冷蔵庫にあったミネラルウォーターを飲んでもらった後、氷水でしぼったタオルをおでこに乗せてあげると一息付いた。
「ありがとな。」
「どういたしまして。けど、廊下で倒れちゃうくらいなのにただの風邪だーなんて!我慢しちゃだめだよ!ほんっとーーーにっびっくりしたんだから!お医者様には行ったの?」
「…行ってない。」
「じゃあ今からは…あ!土曜日だから午後はお休みかぁ…でもうちのかかりつけのお医者様なら連絡すればすぐに診てもらえるよ!?」
「大丈夫。市販の薬の残りもあるし。俺の見立てでは熱さえ下がれば問題ないよ…」
そんな弱々しく微笑まれて言われても全然安心できないよ…っ
「それに、うさが来てくれたし。付き合い始めのころに風邪引いたときは、正直お前の有り余る善意で殺されると思ったけど…」
「むう!弱ってても意地悪言ってー!」
「いや、はは…だけど今はずいぶんしっかり奥さんしてくれてるからな…」
「お、おくさん…///」
そんなっ嬉しそうにそんな事言われたら、私も熱が出そうだよ…っっ
「悪い、まだそんなんじゃないのにな…弱ってると変なこと言っちまうな、俺…」
「変じゃない!だって私、今からいろいろ練習しておくんだもんっ!まもちゃんの自慢の奥さんになれるように。」
「かわいいこと、言ってくれるんだな…」
すっと、右手が私の頬に触れて、そのいつもより高い温度のそれに頬から耳を撫でられるとバクンと心臓が跳ね上がる。
「ねえ奥さん、甘えて、いい?」
「…!!」
私をじっと見つめるその瞳はとろりと甘くて目が離せない。
「まもちゃ…」
そんな中、測ってた体温計のアラームが鳴った。
慌てたように右手を離してそれを見たまもちゃんは、真っ赤な顔のまま貸してと言う私になかなか渡してくれない。
「も、もーまもちゃん!見せて!」
「…見ても、驚くなよ…?」
そう言って熱で(?)真っ赤な顔したまもちゃんが拗ねた様子で渡してくる。
それはさっきの雰囲気とはがらりと違って子供みたいで。風邪を引いたまもちゃんは私の心臓を何度も跳ねさせる。
「って、39.9℃ーーーー!!??」
「く…っうさ…頭に響、く…」
「あ、ごめん。って、私タオル代えてくるっ!お布団ももう一枚出してくるからねっっ!!」
「うさたのむ いまはおおごえ やめてくれ」
一瞬の甘い空気も吹っ飛んで、うわごとみたいなことを言ってるまもちゃんを残して私は部屋を猛ダッシュで出て行った。
ひいいいいっ風邪引いたまもちゃん心臓に悪い!早く良くなってもらわなきゃ…うさぎちゃんの頭が溶けちゃうからーーーー!!
さっきの言葉と掠れた声。触れられた頬と耳。その体温。それを思い出した私は鳴り止まないドキドキを胸に、心の中で叫んだ。