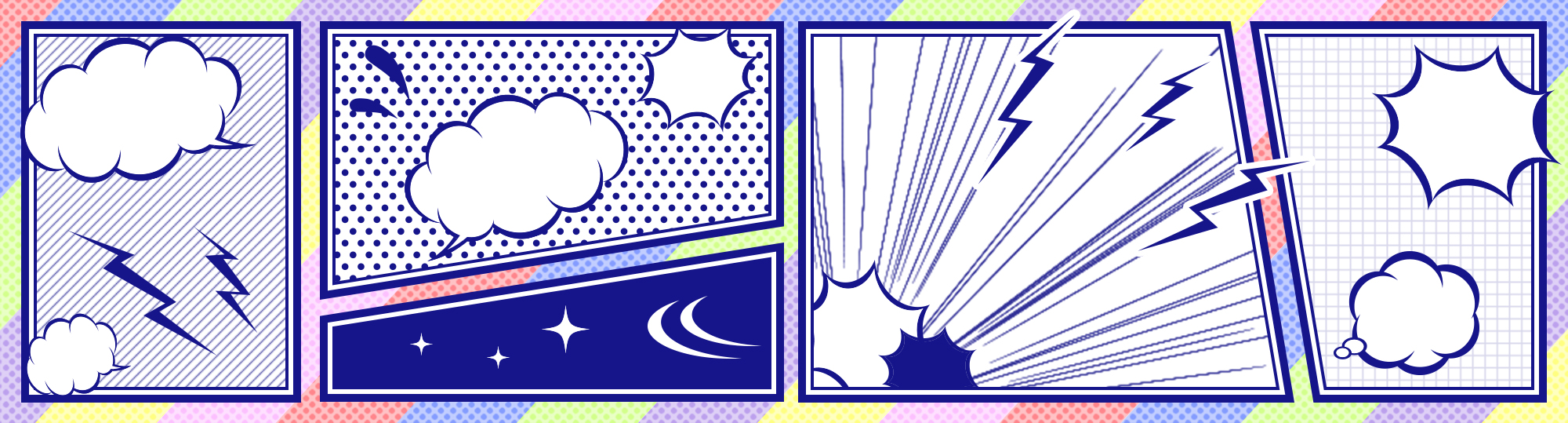夢だけど夢じゃない
はじめにお名前変換してください
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「ま〜〜なぁんでお粗末兄さんと二人きりだったのかは見過ごせないわけだけどォ、こうやってみーんな呼んでくれるってやっぱり名前ちゃん最高に気が効くよねぇ〜」
「あははトド松ぅ、お兄ちゃんの字が違うよぉ?」
「お粗末兄さんうるさーい」
「お?わざとか?わざとなの?喧嘩売ってる?」
普段行く居酒屋に呼び出されたオレたちむつごはそこで待っていたおそ松、名前と一緒にテーブルを囲んでいる。
おそ松から自宅に電話があり「競馬バカ勝ちしたから飲むぞ!」と呼び出された時は何かの罠かと思ったが、恐る恐る飲み屋の扉を開ければそこには既に飲み始めているおそ松と申し訳なさそうに縮こまった名前が広いテーブルに座って待っていた。
「名前ちゃんスッゲーね!ビギナーズラックだね!!」
「ありがとう…でもみんなの(おう松さんの)おかげだから…」
「え?ぼくたち何かした!?!?」
いつもなら迷わず隣に座るが、先程の出来事が気まずくて一松と二人でモダモダしているうちに元々おそ松が隣に座っていてもう片方しか空いてなかった隣には十四松が座っていた。
あれよあれよという間にチョロ松とトド松が席についてしまったためオレと一松は一番端に仕方なく落ち着いたというわけだ。
「というわけで、今日は私の奢りなので好きに飲み食いしてください!」
「いやいや、いくら勝ったからって流石に悪いよ…」
「いえ、こういうギャンブルでお金を得たことがなくて…どう使って良いかわからないので普段お世話になってる皆さんに還元出来たらと思って」
「いや僕たち会うの数回目だし全然お世話なんて…」
「えっと…私が皆さんと楽しく飲みたかった…じゃ、ダメですか?」
「ダメじゃなああ〜〜い!!!全っっっ然ダメじゃなああ〜〜い!!!!!!」
真面目ぶったチョロ松がそれらしいことを言って申し訳なさがったが名前が困ったように笑いかけただけで目をハートにして鼻血を出しながら掌返しするのを少し離れたところからただ眺める。なぜか胸の奥が熱く灼ける感触がして目をそらす。大好きなブラザーたちが大好きな名前と仲良くなるのは嬉しいことのはずなのに、仲良く話すのを見ると胸と腹の間らへんがズクズクと熱くなって気持ち悪いし気分も悪くなる。
原因不明な胸やけに首を傾げながら乾杯のビールグラスをぶつけ合った。
飲めない酒のグラスを傾けながらぼんやりしていたら突然弁慶の泣き所に痛みが走ってハッと顔を上げる。
テーブルの下で俺の脛を軽く蹴ってきた対面の一松と目が合う。気だるげなその目は俺の瞳を捉えたあと、すっと俺の斜め上を見た。その目線を追えば、名前がちょっとお手洗いに、と立ち上がってちょうど俺の後ろを通り過ぎようとしているところだった。
背中を通り過ぎる感覚だけ感じながら一松に目を戻せば、少し眉根を寄せた弟はジッとオレを見たあとテーブルの下、オレの椅子の横に立てかけてある紙袋に目線をやった。中身は名前のふわふわコート。頬杖をついてガラ悪く睨みつけてくる一松に首を傾げれば、チッという舌打ちのあと聞き取れないくらいの小声で「みんなが見てない時の方が良いんじゃないの」と零した。
弟が何を言っているのかやっとわかったオレは弾かれるように立ち上がって紙袋を引っ掴んで店の奥へと足早に向かう。盛り上がっていたテーブルでオレが突然席を外しても誰も見咎める者はいなかった。
「あれっもしかして並んでた?お待たせしてごめんね」
間接照明の効いた薄暗く狭い廊下、トイレ前で待っていると、目の前のドアが開いて名前が顔を覗かせた。ここトイレ1つしかないんだねなどと言って去ろうとする名前の行く手を阻むように壁に寄りかかって見下ろす。名前の戸惑ったように揺れる瞳の中がオレでいっぱいになっているのを見て先ほどズクズク疼いた場所がすっと楽になるのを感じ、自然と口角が上がる。
「…これ」
「あ、私のコート」
「今日はこれを取りに来たんだろう?バタバタして渡せずすまない。コート無しで寒かっただろ?」
「んーん!行きは車だったしさっきまではおそ松くんが上着貸してくれていたから大丈夫!こちらこそ半纏持って帰っちゃってごめんね、カラ松くんこそ寒かったんじゃない?」
渡した紙袋の中身を確認して笑顔を見せた名前に心配の眼差しを向けられるも、その前の爆弾発言のせいでうまく反応出来ない。
おそ松の上着を借りていた?
オレらが店に着いた時にはもう二人とも薄着で着席していたから気付かなかったが、二人で競馬に行っている間ずっとおそ松の上着を着ていたというのか?
痛みが引いたはずの胃の上がまたカーッと熱くなって吐きそうだ。心臓もギュッとなって心なしか速い。思わず胸元を握り締めて眉根を寄せたオレを更に心配するようにカラ松くん?と一歩近付いて伸ばした名前の手をガシッと掴んだ。彼女の肩がびくりと揺れるが構っていられない。おそ松の上着を着ていたということも見過ごせないが、そうだ、コート。なぜ今日まで返せなかったか。渡しに走ったあの日の光景がフラッシュバックする。見知らぬ男の運転する高級車に乗った名前の横顔。そのあまりの衝撃に記憶だというのにチカチカと目の前が光って手に力が入る。遠慮なく握られた手を引きながら痛…っと零した名前の声にハッとして力を緩めた。
「カラ松くんどうし…」
「なぁ、あれ、誰だったんだ?」
本日2度目のその質問に一瞬でなんのことかわかったらしい名前は僅かに目を見開いたあとオロオロと目線を彷徨わせた。
即答してくれないことにイラついたオレは何かやましい関係なのかと言いかけて口を噤んだ。彼女が何か言いかけたからだ。
「…なんだ?」
「…ッ、ハタ坊、の、会社関係の人だよ」
「頭に旗は無かったようだが」
「取引先の他社の人だから…偶然会って、歩きじゃ約束に間に合わなさそうだったから乗せて貰ったの。車でビルの下まで送ってもらっただけだよ」
本当にそれだけ。ハタ坊との約束がなかったら歩いて帰ったよ。そう言うとまっすぐ見つめ返してきた。嘘を言っているようには思えない綺麗な瞳だった。
「追いかけてきてくれてたって知らなくて、気づかなくてごめんね」
オレが掴んだままだった手を、逆にギュッと握られて胸を熱く燻らせていたものが霧散するのを感じた。
無意識に空いている方の手を名前の頬に伸ばし、その柔らかく触り心地の良いすべすべの肌を包み込んだ。もちもちふわふわの頬が気持ち良い。
ずっと裏切られたような気持ちがぐるぐる腹のなかにいたけれど、それもいつの間にかいなくなっていた。
むにむにとやわく頬を揉みながら目線を合わす。薄っすら顔を紅潮させた名前がまっすぐこちらを見上げていて、たまらなくなって握った手の力を緩め、そのまま指をするりと絡ませる。ギョッとしたように手の方へ目線を落とした名前に再び目を見て欲しくて、尖らした口から飛び出た声はあまりに弱々しいものだった。
「……電話したんだ」
「…えっ?」
「約束したろう?毎日電話するって。コート返せなかったあの日、その…タシャノヒト?の助手席に乗ってるの見て…あれ誰?って聞きたくて…でも出ないし…LINEも!したんだ…でも既読つかないし…あれから今日まで毎日電話かけたしLINEも送ったのに一切連絡つかなくてそれで…」
「エッあっごめん!スマホ、コートのポケットに…!」
せっかく絡めていた指を振りほどいて持っていた紙袋からコートをガサゴソ漁るとふわふわの毛皮の中からスマホを取り出してオレの目の前に突き出してくる名前にぱちくりと瞬きを返す。
オレがスマホを認識したのを確認した名前はスイスイと操作をして「うわっメッセージも着信もめっちゃきてる…ごめんね…」と眉を八の字に下げた。
なんだ。連絡がつかなかったのは、スマホがうちにあったからだったんだ。なんだ。なんだ…
はぁ〜〜〜と溜息をついてズルズルしゃがみ込む。嫌われたわけじゃなかった。あの男と何かあったわけでもなかった。ここ数日のイライラや不安が全て溶けたような安心感に包まれていると、オレと目線を合わすようにしゃがみ込んで覗き込んできた名前の心配そうな顔と目が合う。
「なぁ、これからはおやすみのメッセージもおはようのモーニングコールも出てくれるか?」
「…うん」
彼女が頷いたことが嬉しくて嬉しくて胸が熱くなったけれど、さっきまでの嫌な感じではなくてあったかくなるような幸せな気持ちだった。
「あははトド松ぅ、お兄ちゃんの字が違うよぉ?」
「お粗末兄さんうるさーい」
「お?わざとか?わざとなの?喧嘩売ってる?」
普段行く居酒屋に呼び出されたオレたちむつごはそこで待っていたおそ松、名前と一緒にテーブルを囲んでいる。
おそ松から自宅に電話があり「競馬バカ勝ちしたから飲むぞ!」と呼び出された時は何かの罠かと思ったが、恐る恐る飲み屋の扉を開ければそこには既に飲み始めているおそ松と申し訳なさそうに縮こまった名前が広いテーブルに座って待っていた。
「名前ちゃんスッゲーね!ビギナーズラックだね!!」
「ありがとう…でもみんなの(おう松さんの)おかげだから…」
「え?ぼくたち何かした!?!?」
いつもなら迷わず隣に座るが、先程の出来事が気まずくて一松と二人でモダモダしているうちに元々おそ松が隣に座っていてもう片方しか空いてなかった隣には十四松が座っていた。
あれよあれよという間にチョロ松とトド松が席についてしまったためオレと一松は一番端に仕方なく落ち着いたというわけだ。
「というわけで、今日は私の奢りなので好きに飲み食いしてください!」
「いやいや、いくら勝ったからって流石に悪いよ…」
「いえ、こういうギャンブルでお金を得たことがなくて…どう使って良いかわからないので普段お世話になってる皆さんに還元出来たらと思って」
「いや僕たち会うの数回目だし全然お世話なんて…」
「えっと…私が皆さんと楽しく飲みたかった…じゃ、ダメですか?」
「ダメじゃなああ〜〜い!!!全っっっ然ダメじゃなああ〜〜い!!!!!!」
真面目ぶったチョロ松がそれらしいことを言って申し訳なさがったが名前が困ったように笑いかけただけで目をハートにして鼻血を出しながら掌返しするのを少し離れたところからただ眺める。なぜか胸の奥が熱く灼ける感触がして目をそらす。大好きなブラザーたちが大好きな名前と仲良くなるのは嬉しいことのはずなのに、仲良く話すのを見ると胸と腹の間らへんがズクズクと熱くなって気持ち悪いし気分も悪くなる。
原因不明な胸やけに首を傾げながら乾杯のビールグラスをぶつけ合った。
飲めない酒のグラスを傾けながらぼんやりしていたら突然弁慶の泣き所に痛みが走ってハッと顔を上げる。
テーブルの下で俺の脛を軽く蹴ってきた対面の一松と目が合う。気だるげなその目は俺の瞳を捉えたあと、すっと俺の斜め上を見た。その目線を追えば、名前がちょっとお手洗いに、と立ち上がってちょうど俺の後ろを通り過ぎようとしているところだった。
背中を通り過ぎる感覚だけ感じながら一松に目を戻せば、少し眉根を寄せた弟はジッとオレを見たあとテーブルの下、オレの椅子の横に立てかけてある紙袋に目線をやった。中身は名前のふわふわコート。頬杖をついてガラ悪く睨みつけてくる一松に首を傾げれば、チッという舌打ちのあと聞き取れないくらいの小声で「みんなが見てない時の方が良いんじゃないの」と零した。
弟が何を言っているのかやっとわかったオレは弾かれるように立ち上がって紙袋を引っ掴んで店の奥へと足早に向かう。盛り上がっていたテーブルでオレが突然席を外しても誰も見咎める者はいなかった。
「あれっもしかして並んでた?お待たせしてごめんね」
間接照明の効いた薄暗く狭い廊下、トイレ前で待っていると、目の前のドアが開いて名前が顔を覗かせた。ここトイレ1つしかないんだねなどと言って去ろうとする名前の行く手を阻むように壁に寄りかかって見下ろす。名前の戸惑ったように揺れる瞳の中がオレでいっぱいになっているのを見て先ほどズクズク疼いた場所がすっと楽になるのを感じ、自然と口角が上がる。
「…これ」
「あ、私のコート」
「今日はこれを取りに来たんだろう?バタバタして渡せずすまない。コート無しで寒かっただろ?」
「んーん!行きは車だったしさっきまではおそ松くんが上着貸してくれていたから大丈夫!こちらこそ半纏持って帰っちゃってごめんね、カラ松くんこそ寒かったんじゃない?」
渡した紙袋の中身を確認して笑顔を見せた名前に心配の眼差しを向けられるも、その前の爆弾発言のせいでうまく反応出来ない。
おそ松の上着を借りていた?
オレらが店に着いた時にはもう二人とも薄着で着席していたから気付かなかったが、二人で競馬に行っている間ずっとおそ松の上着を着ていたというのか?
痛みが引いたはずの胃の上がまたカーッと熱くなって吐きそうだ。心臓もギュッとなって心なしか速い。思わず胸元を握り締めて眉根を寄せたオレを更に心配するようにカラ松くん?と一歩近付いて伸ばした名前の手をガシッと掴んだ。彼女の肩がびくりと揺れるが構っていられない。おそ松の上着を着ていたということも見過ごせないが、そうだ、コート。なぜ今日まで返せなかったか。渡しに走ったあの日の光景がフラッシュバックする。見知らぬ男の運転する高級車に乗った名前の横顔。そのあまりの衝撃に記憶だというのにチカチカと目の前が光って手に力が入る。遠慮なく握られた手を引きながら痛…っと零した名前の声にハッとして力を緩めた。
「カラ松くんどうし…」
「なぁ、あれ、誰だったんだ?」
本日2度目のその質問に一瞬でなんのことかわかったらしい名前は僅かに目を見開いたあとオロオロと目線を彷徨わせた。
即答してくれないことにイラついたオレは何かやましい関係なのかと言いかけて口を噤んだ。彼女が何か言いかけたからだ。
「…なんだ?」
「…ッ、ハタ坊、の、会社関係の人だよ」
「頭に旗は無かったようだが」
「取引先の他社の人だから…偶然会って、歩きじゃ約束に間に合わなさそうだったから乗せて貰ったの。車でビルの下まで送ってもらっただけだよ」
本当にそれだけ。ハタ坊との約束がなかったら歩いて帰ったよ。そう言うとまっすぐ見つめ返してきた。嘘を言っているようには思えない綺麗な瞳だった。
「追いかけてきてくれてたって知らなくて、気づかなくてごめんね」
オレが掴んだままだった手を、逆にギュッと握られて胸を熱く燻らせていたものが霧散するのを感じた。
無意識に空いている方の手を名前の頬に伸ばし、その柔らかく触り心地の良いすべすべの肌を包み込んだ。もちもちふわふわの頬が気持ち良い。
ずっと裏切られたような気持ちがぐるぐる腹のなかにいたけれど、それもいつの間にかいなくなっていた。
むにむにとやわく頬を揉みながら目線を合わす。薄っすら顔を紅潮させた名前がまっすぐこちらを見上げていて、たまらなくなって握った手の力を緩め、そのまま指をするりと絡ませる。ギョッとしたように手の方へ目線を落とした名前に再び目を見て欲しくて、尖らした口から飛び出た声はあまりに弱々しいものだった。
「……電話したんだ」
「…えっ?」
「約束したろう?毎日電話するって。コート返せなかったあの日、その…タシャノヒト?の助手席に乗ってるの見て…あれ誰?って聞きたくて…でも出ないし…LINEも!したんだ…でも既読つかないし…あれから今日まで毎日電話かけたしLINEも送ったのに一切連絡つかなくてそれで…」
「エッあっごめん!スマホ、コートのポケットに…!」
せっかく絡めていた指を振りほどいて持っていた紙袋からコートをガサゴソ漁るとふわふわの毛皮の中からスマホを取り出してオレの目の前に突き出してくる名前にぱちくりと瞬きを返す。
オレがスマホを認識したのを確認した名前はスイスイと操作をして「うわっメッセージも着信もめっちゃきてる…ごめんね…」と眉を八の字に下げた。
なんだ。連絡がつかなかったのは、スマホがうちにあったからだったんだ。なんだ。なんだ…
はぁ〜〜〜と溜息をついてズルズルしゃがみ込む。嫌われたわけじゃなかった。あの男と何かあったわけでもなかった。ここ数日のイライラや不安が全て溶けたような安心感に包まれていると、オレと目線を合わすようにしゃがみ込んで覗き込んできた名前の心配そうな顔と目が合う。
「なぁ、これからはおやすみのメッセージもおはようのモーニングコールも出てくれるか?」
「…うん」
彼女が頷いたことが嬉しくて嬉しくて胸が熱くなったけれど、さっきまでの嫌な感じではなくてあったかくなるような幸せな気持ちだった。