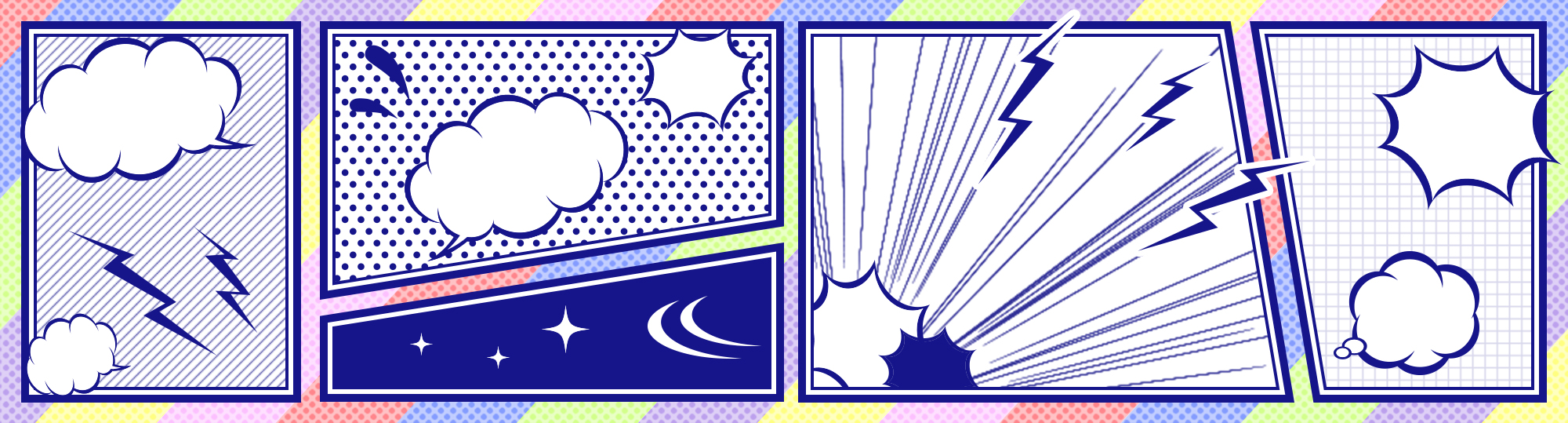夢だけど夢じゃない
はじめにお名前変換してください
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
玄関で泣き崩れた彼女の手を咄嗟に引っ張り上げてそのまま二階へ連れ込んだのは英断だったと誰か褒めて欲しい。
居間にいるあのクソブスに悟られないように二階のおれらの部屋に彼女を連れていってしゃくり上げる彼女の前に箱ティッシュを置く。
泣き続ける彼女に兄弟3人でオロオロするもどうしたらいいのか誰もわからない。十四松が優しく頭を撫でて背中を撫でているのを対面で座り込んで見守ったまま思案する。
確かに散々親友だ特別だと宣っていたあのクソ松があんなバケモノ囲ってた上に優先順位がそっちのが上だと言われたらショックだろう。
正直、今あいつの中での優先順位最上位はあのバケモノなわけで、今迄優先順位上位を占めていたおれら兄弟ですら若干ショックを受けている。
「名前ちゃんはカラ松兄さんのことが大好きなんだねえ〜」
十四松の間延びした声のせいで重要な内容が一瞬入ってこなかった。
はっ?なんて?
「はっ?なんて?」
トド松がおれの心と全く同じことを言った。
「う、うっうん…しんゆ、だか、ら…ッ」
「そーなの?名前ちゃんのスキは親友のスキなの?」
ゆっくり背中を撫でながら伸びきった袖で彼女の頰を擦り涙を拭いつつ、諭すような声音で優しく問いかける五男。
ぼろぼろ涙を零しながらしゃくり上げていた彼女はぐっと唇を噛み締めると勢いよく首を振った。横に。
雷に撃たれた衝撃だった。
実際、隣の末弟は雷に撃たれて黒焦げになってそのままばたりと畳に伏して動かなくなった。
「だよねぇ。よしよし」
何もかもお見通しのような発言をして十四松が彼女を優しく抱き締めるとその胸に顔を埋めた彼女が堰を切ったようにわんわん泣き出した。優しく頭を撫で続ける十四松は菩薩のような顔をしていて、一見いちゃついているような体勢の2人が、聖母に抱かれたこどものように見えて口すら出せない。
結局、彼女が泣き止んで落ち着くまで出来ることもないので、おれは人数分のお茶を台所で淹れていた。
茶の間では横になってテレビを見ながらアイスを食べているバケモノとその横にぴったりくっついた青いクソの背中が見える。そこで何やってんだよクソ松。上に彼女がいることわかってねえのかよクソ松。
今にも殺さんばかりの視線を送るも一向に気付かれることはなく、聞こえるように大きな舌打ちをすると湯呑みを盆にのせてドスドスと階段を上がった。
「あ、一松くん…ありがとう…」
脚で襖を開ければ、すっかり焦燥して目元を真っ赤に腫らした痛々しい彼女がこちらを向いて微笑んだ。そんな顔しなくていい。胸が痛んで、後ろ足で襖を閉めると真っ先に彼女に湯呑みを渡した。
ふぅふぅと息を吹きかけ少し口をつけると、美味しい、と笑った彼女に心の奥がちくりと痛む。
十四松とトド松の間に座った彼女は黙ってお茶を飲み続けて湯呑みを空っぽにした。
「………お代わりあるけど」
「あっ、いただきます」
そう言って盆の上の急須を取ると、湯呑みが差し向けられる。そうっと注げば両手で湯呑みを持っていた彼女が陶器越しに伝わった熱にあちちと言いながらはにかむように笑った。かわいい。こんなかわいいこの子を泣かせるなんて何やってんだよクソ松。奥歯を噛み締めたせいでギリ…という嫌な音が鳴った。
「………名前ちゃん、クソ松兄さんのことが好きなの?恋愛的な意味で」
なぜかこちらも目元を真っ赤に腫らしたトド松がぷーっと頰を膨らませたまま吐き捨てるように掘り返した。
彼女はドキッとしたような顔をして目線をあちこちに飛ばしたが、安心させるように背を撫でた十四松の方を恐る恐る見ると目線を落として小さく頷いた。
ああ、そうだったのか、と思うより前に隣のトド松がアーーーーッッッと大声を上げて大の字に倒れたのでびくっとする。え、なにこいつ。
「何それ何それぇ…ええ…馬鹿みたい…ボク馬鹿みたいじゃん…えええ〜〜なんで?いつから?なんで?なんでよりによってあのクソ松兄さん?見た?あんなバケモノ連れ込んで飼ってるヤバイ奴だよ???」
自暴自棄になったらしい末弟が寝転がったままジタバタして叫ぶように言った。
バカ、下に聞こえたらどうする…
そわそわしながら入り口の襖と暴れる末弟を見比べていたら自嘲気味に笑った彼女が「ずっと前から好きだったんです、諦めようとしてたんですけど」と零した。
あ、そう…そうなんだ…
おれも何故クソ松?という疑問はあったけど「好きに理由は必要ないもんねえ」と穏やかに言う十四松にそういうものなのか、と口をつぐむ。
彼女らしき人物がいた唯一の兄弟の言うことは聞こう。
「…みんなが仲良くしてくれるのは嬉しかった、親友でも特別ならそれで良いかと思ってた、でも」
特別扱いされるたびに期待して、親友と言われるたびに傷ついて…そこまで言ってハッとしたように彼女がおれを見た。急に注目されて思わず座ったまま後ずさる。
「ごめんなさい一松くん…!私、自分がされて嫌だったこと、一松くんにしてた…一方的に友達って言って…そう言われたら友達って返すしかないのに…」
「えっ?いや、大丈夫、おれ名前ちゃんのこと好きだけどそういう好きじゃないし友達になりたいって言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しかったっていうか…だからその…」
何言ってんだおれ!?!?
ベラベラと恥ずかしいことを口走ってしまい真っ赤になっているのがわかる。
ひっくり返っていたトド松が勢い良く起き上がるとハ!?なに!?友達になりたいって!?言われた!?!?いつ!?!?何それ!?!?なんでみんなボクの知らないとこで抜け駆けしてるわけ!?裏切り者!とか騒いでいるのを無視してちらりと名前ちゃんを見れば、天使みたいな顔をして泣きそうなのを堪えながら笑っていた。ありがとうと口が動いた気がする。えっ天使か?
動揺していると十四松がガバッと名前ちゃんを覗き込んで「ぼくも友達だよね!?」と聞いた。彼女はキョトンとしたあとに花がほころぶように笑って頷く。うわあ〜〜かわいい〜〜〜〜おれの友達かわいい〜〜えっ恐れ多い明日死ぬのか?
「………んで?名前ちゃんはどうしたいわけ」
心底不機嫌そうな声でトド松が吐き捨てる。
どうって…とおろおろする彼女をキッと睨み付けると「付き合いたいんなら応援するよ?ボクだって名前ちゃんに幸せになってもらいたいし?でも現状に甘んじるならボクもそれ相応の対応をとるから!」と指を突きつけた。それ相応の対応ってなんだ?何言ってんだこいつ。
「…付き合いたくっても、私だけがそう思ってても仕方ないので」
「そ、そりゃそうかもしれないけど〜〜〜〜」
曖昧な答えを返した彼女は、ご迷惑をお掛けしました、カラ松くんの特別でいられるなら良いんです今のままで、このことは絶対カラ松くんには言わないでくださいね、と言うと去っていった。
彼女を見送って二階の和室に戻ってきたおれらは階下から聞こえる甘ったるいやり取りに吐き気を催す。
既に特別でいられてないじゃん。今の特別はあのブスじゃん。
こういうことに慣れてなくて気の利いたことを一つも言えなかったけど、それくらいはわかる。
ぼんやり隅っこに座ると、拳をソファに叩きつけたトッティが立ち上がったのでゆるりとそちらを見やる。
「ボク諦めないから。あんなドブスにうつつを抜かしてるようなクソ松兄さんに取られてたまるか」
何かの決意表明をしたらしいトド松はフンスと鼻息荒く再び座った。何こいつ。
友達として何か出来ることがあるのかな。
膝に顔を埋めて考えに沈んでいると、窓から入ってきたらしい猫が足元にすり寄ってきた。
「ねえ、何が出来ると思う?」
猫 に話しかけながら抱き上げれば、したり顔の猫はニャアと鳴いた。
居間にいるあのクソブスに悟られないように二階のおれらの部屋に彼女を連れていってしゃくり上げる彼女の前に箱ティッシュを置く。
泣き続ける彼女に兄弟3人でオロオロするもどうしたらいいのか誰もわからない。十四松が優しく頭を撫でて背中を撫でているのを対面で座り込んで見守ったまま思案する。
確かに散々親友だ特別だと宣っていたあのクソ松があんなバケモノ囲ってた上に優先順位がそっちのが上だと言われたらショックだろう。
正直、今あいつの中での優先順位最上位はあのバケモノなわけで、今迄優先順位上位を占めていたおれら兄弟ですら若干ショックを受けている。
「名前ちゃんはカラ松兄さんのことが大好きなんだねえ〜」
十四松の間延びした声のせいで重要な内容が一瞬入ってこなかった。
はっ?なんて?
「はっ?なんて?」
トド松がおれの心と全く同じことを言った。
「う、うっうん…しんゆ、だか、ら…ッ」
「そーなの?名前ちゃんのスキは親友のスキなの?」
ゆっくり背中を撫でながら伸びきった袖で彼女の頰を擦り涙を拭いつつ、諭すような声音で優しく問いかける五男。
ぼろぼろ涙を零しながらしゃくり上げていた彼女はぐっと唇を噛み締めると勢いよく首を振った。横に。
雷に撃たれた衝撃だった。
実際、隣の末弟は雷に撃たれて黒焦げになってそのままばたりと畳に伏して動かなくなった。
「だよねぇ。よしよし」
何もかもお見通しのような発言をして十四松が彼女を優しく抱き締めるとその胸に顔を埋めた彼女が堰を切ったようにわんわん泣き出した。優しく頭を撫で続ける十四松は菩薩のような顔をしていて、一見いちゃついているような体勢の2人が、聖母に抱かれたこどものように見えて口すら出せない。
結局、彼女が泣き止んで落ち着くまで出来ることもないので、おれは人数分のお茶を台所で淹れていた。
茶の間では横になってテレビを見ながらアイスを食べているバケモノとその横にぴったりくっついた青いクソの背中が見える。そこで何やってんだよクソ松。上に彼女がいることわかってねえのかよクソ松。
今にも殺さんばかりの視線を送るも一向に気付かれることはなく、聞こえるように大きな舌打ちをすると湯呑みを盆にのせてドスドスと階段を上がった。
「あ、一松くん…ありがとう…」
脚で襖を開ければ、すっかり焦燥して目元を真っ赤に腫らした痛々しい彼女がこちらを向いて微笑んだ。そんな顔しなくていい。胸が痛んで、後ろ足で襖を閉めると真っ先に彼女に湯呑みを渡した。
ふぅふぅと息を吹きかけ少し口をつけると、美味しい、と笑った彼女に心の奥がちくりと痛む。
十四松とトド松の間に座った彼女は黙ってお茶を飲み続けて湯呑みを空っぽにした。
「………お代わりあるけど」
「あっ、いただきます」
そう言って盆の上の急須を取ると、湯呑みが差し向けられる。そうっと注げば両手で湯呑みを持っていた彼女が陶器越しに伝わった熱にあちちと言いながらはにかむように笑った。かわいい。こんなかわいいこの子を泣かせるなんて何やってんだよクソ松。奥歯を噛み締めたせいでギリ…という嫌な音が鳴った。
「………名前ちゃん、クソ松兄さんのことが好きなの?恋愛的な意味で」
なぜかこちらも目元を真っ赤に腫らしたトド松がぷーっと頰を膨らませたまま吐き捨てるように掘り返した。
彼女はドキッとしたような顔をして目線をあちこちに飛ばしたが、安心させるように背を撫でた十四松の方を恐る恐る見ると目線を落として小さく頷いた。
ああ、そうだったのか、と思うより前に隣のトド松がアーーーーッッッと大声を上げて大の字に倒れたのでびくっとする。え、なにこいつ。
「何それ何それぇ…ええ…馬鹿みたい…ボク馬鹿みたいじゃん…えええ〜〜なんで?いつから?なんで?なんでよりによってあのクソ松兄さん?見た?あんなバケモノ連れ込んで飼ってるヤバイ奴だよ???」
自暴自棄になったらしい末弟が寝転がったままジタバタして叫ぶように言った。
バカ、下に聞こえたらどうする…
そわそわしながら入り口の襖と暴れる末弟を見比べていたら自嘲気味に笑った彼女が「ずっと前から好きだったんです、諦めようとしてたんですけど」と零した。
あ、そう…そうなんだ…
おれも何故クソ松?という疑問はあったけど「好きに理由は必要ないもんねえ」と穏やかに言う十四松にそういうものなのか、と口をつぐむ。
彼女らしき人物がいた唯一の兄弟の言うことは聞こう。
「…みんなが仲良くしてくれるのは嬉しかった、親友でも特別ならそれで良いかと思ってた、でも」
特別扱いされるたびに期待して、親友と言われるたびに傷ついて…そこまで言ってハッとしたように彼女がおれを見た。急に注目されて思わず座ったまま後ずさる。
「ごめんなさい一松くん…!私、自分がされて嫌だったこと、一松くんにしてた…一方的に友達って言って…そう言われたら友達って返すしかないのに…」
「えっ?いや、大丈夫、おれ名前ちゃんのこと好きだけどそういう好きじゃないし友達になりたいって言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しかったっていうか…だからその…」
何言ってんだおれ!?!?
ベラベラと恥ずかしいことを口走ってしまい真っ赤になっているのがわかる。
ひっくり返っていたトド松が勢い良く起き上がるとハ!?なに!?友達になりたいって!?言われた!?!?いつ!?!?何それ!?!?なんでみんなボクの知らないとこで抜け駆けしてるわけ!?裏切り者!とか騒いでいるのを無視してちらりと名前ちゃんを見れば、天使みたいな顔をして泣きそうなのを堪えながら笑っていた。ありがとうと口が動いた気がする。えっ天使か?
動揺していると十四松がガバッと名前ちゃんを覗き込んで「ぼくも友達だよね!?」と聞いた。彼女はキョトンとしたあとに花がほころぶように笑って頷く。うわあ〜〜かわいい〜〜〜〜おれの友達かわいい〜〜えっ恐れ多い明日死ぬのか?
「………んで?名前ちゃんはどうしたいわけ」
心底不機嫌そうな声でトド松が吐き捨てる。
どうって…とおろおろする彼女をキッと睨み付けると「付き合いたいんなら応援するよ?ボクだって名前ちゃんに幸せになってもらいたいし?でも現状に甘んじるならボクもそれ相応の対応をとるから!」と指を突きつけた。それ相応の対応ってなんだ?何言ってんだこいつ。
「…付き合いたくっても、私だけがそう思ってても仕方ないので」
「そ、そりゃそうかもしれないけど〜〜〜〜」
曖昧な答えを返した彼女は、ご迷惑をお掛けしました、カラ松くんの特別でいられるなら良いんです今のままで、このことは絶対カラ松くんには言わないでくださいね、と言うと去っていった。
彼女を見送って二階の和室に戻ってきたおれらは階下から聞こえる甘ったるいやり取りに吐き気を催す。
既に特別でいられてないじゃん。今の特別はあのブスじゃん。
こういうことに慣れてなくて気の利いたことを一つも言えなかったけど、それくらいはわかる。
ぼんやり隅っこに座ると、拳をソファに叩きつけたトッティが立ち上がったのでゆるりとそちらを見やる。
「ボク諦めないから。あんなドブスにうつつを抜かしてるようなクソ松兄さんに取られてたまるか」
何かの決意表明をしたらしいトド松はフンスと鼻息荒く再び座った。何こいつ。
友達として何か出来ることがあるのかな。
膝に顔を埋めて考えに沈んでいると、窓から入ってきたらしい猫が足元にすり寄ってきた。
「ねえ、何が出来ると思う?」