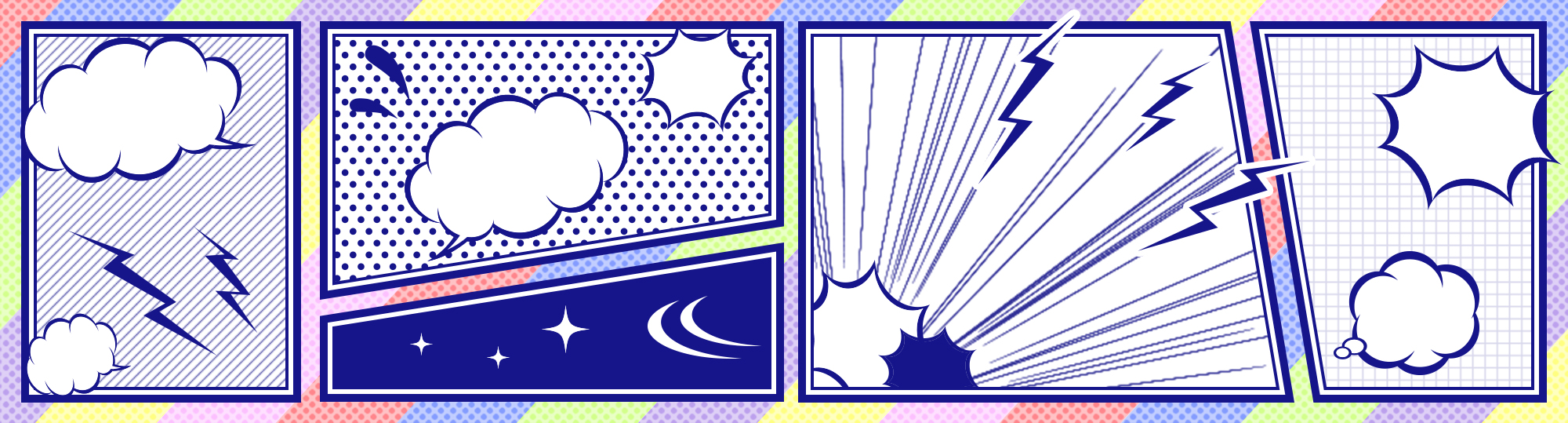夢だけど夢じゃない
はじめにお名前変換してください
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
楽しかった食卓を思い返して上機嫌のまま、やたら重たい紙袋を抱えて家に帰れば俺以外の全員の靴が玄関にあった。食べる前に電話した時は誰も出なかったがみんな帰ってるのか。
底冷えする廊下からスッと襖を開けて茶の間に入れば顔を赤らめた同じ顔が5つこちらを向いた。
「あっカラ松兄さんおかえり〜〜」
「なんだよカラ松ぅ、今更帰ってきて!どこ行ってたんだよ」
「ただいま…随分酔っ払ってるな」
「ふっふーん!なーんと今日はぁ、トト子ちゃんと飲み会だったんですぅ〜〜」
「良いでしょ〜お前も誘おうと思ったけどいなかったから自業自得」
「トト子ちゃんがボクたちと飲んでくれるなんて超珍しいよね〜〜カラ松兄さんざーんねん」
成る程、通りでブラザー達もトト子ちゃんも連絡がつかなかったわけだ。
あまり残念に思わないのは先程までの晩飯が余程楽しかったからだろうなと1人納得して俯いて笑っていると「え、なに、悔しすぎて泣いてんの?」とドン引きしたチョロ松の声がした。
次は参加させてくれ、次なんかないかもよーなどと軽口を叩きあっていたら、うつ伏せに寝転んだ一松の上に座っていた十四松が「カラ松兄さんなにその荷物ー!?!?」と叫んだ。
「ほんとだ、なにそれ」
「パチンコ?パチンコ?」
「なっにぃ〜〜!?カラ松パチンコ行ってたの!?」
「パチンコじゃない、ちょっとお土産に貰ってな。ブラザー達も明日食べよう」
「なになにー?たべものー?」
紙袋を抱え直し、ごろごろ転がる酔っ払ったブラザー達を避けたり跨いだりしながら茶の間を突っ切ると台所の方へ繋がる襖を開ける。
寒〜い早く閉めろ〜とブーイングを背中に浴びながら後ろ手で襖を閉めると、台所のテーブルに紙袋をおろした。
中からポトフがギチギチに詰まった大きなビンを数個取り出す。ちゃぷんとスープが音を立てた。本当に美味しかったな。口約束のポトフを覚えていたことも実際作ってくれたこともワイワイ騒ぎながら一緒に作ったこともコタツを囲んで一緒に食べたことも嬉しくて嬉しくて、先程までの光景を思い返しながらほろ酔いで上機嫌になって冷蔵庫を開けた。冬場とはいえ冷蔵庫にしまった方が良いと思って瓶を1つ鷲掴み、冷蔵庫の空いたスペースを見ようとしゃがみ込んだ目の前に、庫内の冷たい光に照らされた、サンタ帽を被った猫が鎮座していた。無機質でまん丸の瞳と目が合う。
「いちまつ、」と思わず声に出てしまったのは同じ帽子を被った菓子をつい先程見たからだ。兄弟のようだと並べた動物型の菓子。猫がいなくて1つ開けたスペース。これがなぜこんなところに。
冷蔵庫を開けっ放しで食い入るように目の前の菓子を凝視していると、ガタン!と台所の入り口で音がして振り返る。
十四松のケツに敷かれていたはずの赤い顔をしたボサボサ頭が、紫色のパーカーの肩を上下させてすごい表情でこちらを見ていた。
「いちま、」
「何してんの」
「え」
「何してんだよ」
随分慌てて来たのか、下がりかけたズボンを引っ張りあげながらズカズカと入って来た弟は冷蔵庫の扉を引っ掴むとバタン!と乱暴に閉じた。
しゃがみ込んで扉に手をかけたままだった俺は危うく手を挟むところだったがそんなことよりこの短い距離を息切らせてやってきた弟に釘付けだった。
「なんで冷蔵庫開けんだよ」
「え、あ、これをしまおうと…」
「なにこれ」
「ポトフ」
「は?」
「いや、もらって…」
名前に貰った、とは何故か言えなくてまごまごとする俺にチッと大きな舌打ちをすると俺からビンを奪ってバッと冷蔵庫を開けるとさっとビンを突っ込みバタン!とまたすぐに冷蔵庫を閉めてしまった。
「しまった。ほら戻れよ」
「いや、まだある…」
「アァ゛!?!?」
「ヒィ…ッ!!ま、まだビンある…!」
怯えながら机の上のビンを指差せば、人を殺しそうな顔をしたまま両手でビンを引っ掴むと足で冷蔵庫を開けてビンを放り込んだ。
「…いちまつ、」
「ア゛!?!?」
「その、ねこ、お前のか?」
またしても勢い良く冷蔵庫の扉を閉めようとしていた四男の手がぴたりと止まって、こちらに背を向けたまま固まってしまった。開きっぱなしの冷蔵庫の中からサンタの猫マカロンがこちらを見ている。
こちらに背を向けたままの一松は地を這うような声で「………どのねこ」とだけ言った。
「その、上の段にいる…」
「…食べたら殺す」
「それ、どうし…」
「食べたら殺すぞ!!!!ァア゛ンン!?!?」
「たっ食べない!!!!食べない!!!!」
冷蔵庫の扉を開けっ放しにしたままこちらに掴みかかってきた一松のあまりの勢いに泣きながら首を振る。
開けっ放しの冷蔵庫がピーーーーと鳴いた。
舌打ちをした一松が両手は俺の襟ぐりを掴んだまま後ろ足で蹴り飛ばし扉を閉める。
「食べないけど、どこで手に入れたんだ?」
「は?関係ねぇだろ」
食べたら殺す、他のやつに言っても殺す、そう言いながらつき飛ばすように俺から手を離してのしのしと茶の間に戻っていった四男の背をモヤモヤと見送った。
まさか、まさか、な。
あの猫は足りなかったピースなんかじゃない、たまたま同じ店で見つけて買ったんだろう自分で、一松は猫が好きだから。
そう言い聞かせるように納得する。
みんながいる茶の間に行きたくなくて、楽しかった晩餐を反芻しながら暗い階段を登った。
底冷えする廊下からスッと襖を開けて茶の間に入れば顔を赤らめた同じ顔が5つこちらを向いた。
「あっカラ松兄さんおかえり〜〜」
「なんだよカラ松ぅ、今更帰ってきて!どこ行ってたんだよ」
「ただいま…随分酔っ払ってるな」
「ふっふーん!なーんと今日はぁ、トト子ちゃんと飲み会だったんですぅ〜〜」
「良いでしょ〜お前も誘おうと思ったけどいなかったから自業自得」
「トト子ちゃんがボクたちと飲んでくれるなんて超珍しいよね〜〜カラ松兄さんざーんねん」
成る程、通りでブラザー達もトト子ちゃんも連絡がつかなかったわけだ。
あまり残念に思わないのは先程までの晩飯が余程楽しかったからだろうなと1人納得して俯いて笑っていると「え、なに、悔しすぎて泣いてんの?」とドン引きしたチョロ松の声がした。
次は参加させてくれ、次なんかないかもよーなどと軽口を叩きあっていたら、うつ伏せに寝転んだ一松の上に座っていた十四松が「カラ松兄さんなにその荷物ー!?!?」と叫んだ。
「ほんとだ、なにそれ」
「パチンコ?パチンコ?」
「なっにぃ〜〜!?カラ松パチンコ行ってたの!?」
「パチンコじゃない、ちょっとお土産に貰ってな。ブラザー達も明日食べよう」
「なになにー?たべものー?」
紙袋を抱え直し、ごろごろ転がる酔っ払ったブラザー達を避けたり跨いだりしながら茶の間を突っ切ると台所の方へ繋がる襖を開ける。
寒〜い早く閉めろ〜とブーイングを背中に浴びながら後ろ手で襖を閉めると、台所のテーブルに紙袋をおろした。
中からポトフがギチギチに詰まった大きなビンを数個取り出す。ちゃぷんとスープが音を立てた。本当に美味しかったな。口約束のポトフを覚えていたことも実際作ってくれたこともワイワイ騒ぎながら一緒に作ったこともコタツを囲んで一緒に食べたことも嬉しくて嬉しくて、先程までの光景を思い返しながらほろ酔いで上機嫌になって冷蔵庫を開けた。冬場とはいえ冷蔵庫にしまった方が良いと思って瓶を1つ鷲掴み、冷蔵庫の空いたスペースを見ようとしゃがみ込んだ目の前に、庫内の冷たい光に照らされた、サンタ帽を被った猫が鎮座していた。無機質でまん丸の瞳と目が合う。
「いちまつ、」と思わず声に出てしまったのは同じ帽子を被った菓子をつい先程見たからだ。兄弟のようだと並べた動物型の菓子。猫がいなくて1つ開けたスペース。これがなぜこんなところに。
冷蔵庫を開けっ放しで食い入るように目の前の菓子を凝視していると、ガタン!と台所の入り口で音がして振り返る。
十四松のケツに敷かれていたはずの赤い顔をしたボサボサ頭が、紫色のパーカーの肩を上下させてすごい表情でこちらを見ていた。
「いちま、」
「何してんの」
「え」
「何してんだよ」
随分慌てて来たのか、下がりかけたズボンを引っ張りあげながらズカズカと入って来た弟は冷蔵庫の扉を引っ掴むとバタン!と乱暴に閉じた。
しゃがみ込んで扉に手をかけたままだった俺は危うく手を挟むところだったがそんなことよりこの短い距離を息切らせてやってきた弟に釘付けだった。
「なんで冷蔵庫開けんだよ」
「え、あ、これをしまおうと…」
「なにこれ」
「ポトフ」
「は?」
「いや、もらって…」
名前に貰った、とは何故か言えなくてまごまごとする俺にチッと大きな舌打ちをすると俺からビンを奪ってバッと冷蔵庫を開けるとさっとビンを突っ込みバタン!とまたすぐに冷蔵庫を閉めてしまった。
「しまった。ほら戻れよ」
「いや、まだある…」
「アァ゛!?!?」
「ヒィ…ッ!!ま、まだビンある…!」
怯えながら机の上のビンを指差せば、人を殺しそうな顔をしたまま両手でビンを引っ掴むと足で冷蔵庫を開けてビンを放り込んだ。
「…いちまつ、」
「ア゛!?!?」
「その、ねこ、お前のか?」
またしても勢い良く冷蔵庫の扉を閉めようとしていた四男の手がぴたりと止まって、こちらに背を向けたまま固まってしまった。開きっぱなしの冷蔵庫の中からサンタの猫マカロンがこちらを見ている。
こちらに背を向けたままの一松は地を這うような声で「………どのねこ」とだけ言った。
「その、上の段にいる…」
「…食べたら殺す」
「それ、どうし…」
「食べたら殺すぞ!!!!ァア゛ンン!?!?」
「たっ食べない!!!!食べない!!!!」
冷蔵庫の扉を開けっ放しにしたままこちらに掴みかかってきた一松のあまりの勢いに泣きながら首を振る。
開けっ放しの冷蔵庫がピーーーーと鳴いた。
舌打ちをした一松が両手は俺の襟ぐりを掴んだまま後ろ足で蹴り飛ばし扉を閉める。
「食べないけど、どこで手に入れたんだ?」
「は?関係ねぇだろ」
食べたら殺す、他のやつに言っても殺す、そう言いながらつき飛ばすように俺から手を離してのしのしと茶の間に戻っていった四男の背をモヤモヤと見送った。
まさか、まさか、な。
あの猫は足りなかったピースなんかじゃない、たまたま同じ店で見つけて買ったんだろう自分で、一松は猫が好きだから。
そう言い聞かせるように納得する。
みんながいる茶の間に行きたくなくて、楽しかった晩餐を反芻しながら暗い階段を登った。