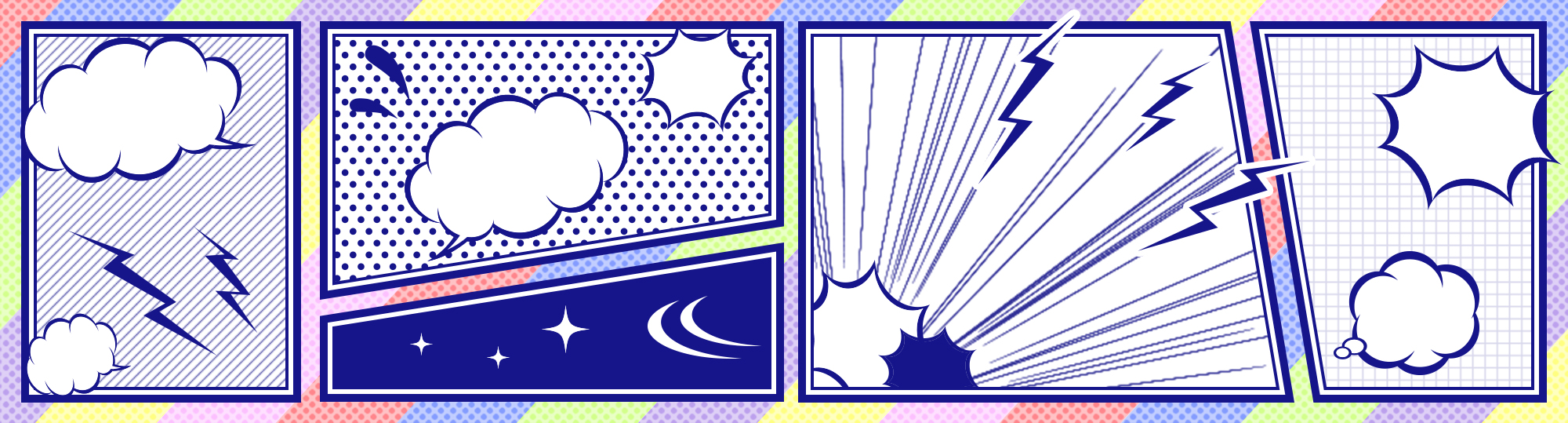夢だけど夢じゃない
はじめにお名前変換してください
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「えっ?就活!?」
いたたまれなくて迎えを呼んで逃げ帰ってから何日経ったんだろう。
カラ松くんの前であんなに取り乱して何を口走ったのか記憶が定かじゃない。じわじわと悟ってはいたけれど、散々脈なしだと思っていたところへ刺激が強すぎてもしかして悪い夢だったんじゃないかとすら思う。
エレベーターの中で電源を落としたスマホはあれから一度も起動してない。いろんな人から連絡が来ているかと思うと怖くて再起動する勇気が持てなかった。置いて帰ってしまったトト子ちゃん、怒ってるだろうな…トッティも一松くんも多分私を連れ出すために来てくれていたんだよね、おそらくカラ松くんも…。差し出された真っ赤な薔薇越しに見た顔が忘れられない。ダズンローズ。それのもつ意味をちゃんとわかって私に差し出されていた。
『いや、名前はオレのこと本当に好きなんだなって』
バレた。ついにバレてしまった。
『なぁ、全然急なんかじゃない、オレは名前のことずっと…』
いや急でしょ!!!!!!!いや、急ではないか…?あんなことやこんなこともあったけど…いやいや、やっぱり急でしょ!!!!なんで!?いつから!?!?どういうこと!?!?!?!?
…なんてジタバタしていたら思いのほか時が経ち、久方ぶりに外に出てふらりと寄ったおでん屋でトト子ちゃんが語学留学に行ったこと、チョロ松くんが就職したこと、トド松くんが家を出たこと、そしてカラ松くんがチビ太家に居候して就活していることを聞いた。目白押しすぎる。もうこれ最終話近いじゃん。私が引きこもっている間にそんなことに…。
「なあ名前ちゃん。あいつ、すげー頑張っててさ。毎日夜中まで履歴書書いて朝早く出て行って…夜遅くに明るく帰ってくるんだけどよ、泣き腫らしたみてーに目の周り赤くしてて…もうオイラ見てらんねーんだ。一回会って慰めてやってくれよ」
「う…実は私、カラ松くんと喧嘩…ではないけど…ちょっといま気まずくて…」
「おーいチビ太~悪いが今日はここで食わしてくれない、か…」
元気よく暖簾をめくって入ってきた男とばっちり目が合う。そんなびっくりした顔する?びっくりしたのはこっちだっての。そっちは外から先客いるの見えてただろ。
見慣れない地味な色味のスーツに身を包んだ松野カラ松が暖簾を片手で押し上げたまま突っ立っていた。あ、とか、う、とか呻いて出ていこうとするカラ松の腕を強引に引っ張って私の隣に座らせた店主は「今日は早いじゃねーか」と言いながら大根とたまごの乗った皿を男の前に出し、帰れない雰囲気を作った。
「……」
「……」
「…なあ、そんな顔して座ってんのよしてくんねぇかな、オイラのおでんが不味いみたいじゃねーか」
わざと不機嫌そうにそう言ってくる店主に、慌てておでんを頬張り笑顔を見せる。だってチビ太くんのおでんは世界一おいしいもん。
おずおずとおでんに手をつけた隣の男に助け舟を出すように店主は明るく最近のカラ松がいかにすごいか、居候はしているけど飲食代は日雇いのバイトとかで稼いだ金で自炊してまかなっていること、おかげでちょっと瘦せたけどバイトと就活で毎日頑張っていてえらい、など面白おかしく説明してみせた。たしかに少し頬の丸みがシャープになっている気がする。
「ただよ~やっぱり男の一人暮らしの家にもうひとり成人男性が転がり込んでくるのは無理があるっていうかよ~…シンプルに狭いんだよな!(笑)ハタ坊んちと違って狭い安アパートだからさあ!」
意味ありげな目配せをしながらケラケラ笑うチビ太のアシストに耐えきれなくなった私は店主の意をくんで「うちくる?」とこぼした。
「…え?」
「うちっていうかハタ坊の家だけど…前にもしばらくいたでしょう?あの時と同じ暮らしなら提供できるし…あの時と違って私も貯金があるからハタ坊に頼らなくても何とかなるし…ハタ坊に言えば今より条件のいいバイトだって…」
「あまえたくない」
「えっ」
「申し出はありがたいが…オレだってもうあの時とは違う。あの時みたいに甘えたくないんだ。あの時名前に救ってもらって…ああ、女神って本当にいたんだって…名前はあの時からずっとオレの特別な存在で…」
「特別な…」
「ああ、そんな顔しないでくれ。たしかにあの時は”特別な親友”だって思ってた。でも今は…いや違うな、あの頃からずっと、出会ったその時からずっと変わらず、名前はオレの…大切なハニーなんだ」
やっとまともに目が合った隣の男はそう言ってはにかむように笑った。ずるい。そんな顔で、そんな声で、そんな大人っぽいスーツ姿で、そんな逃げ場のないこと、そんな勘違いしようのないことを、言うなんて。
「オレ、正社員になるから」
「えっ?」
「まずはバイトから…と思ったがそれで満足して甘えてしまいそうな自分が怖いんだ。実際、就活しながらバイトして…充分だと思ってしまいそうになる。でもそれじゃだめなんだ。それじゃ変われない…名前と釣り合う男になれない。どんな一軍が手を出してきたって引け目を感じないような、そんな正社員になるから…そしたら…つきあってほしい」
「…ど、どこへ」
「フッ、わかっているくせに小悪魔だな…。はっきり言う。オレの彼女になってほしい」
ず、ずるい!!!!!!そんな顔で(以下略)
目をそらせずに口をぱくぱくさせていると愛おしそうに目を細めたカラ松が皿の上の最後のひとかけらを口に放り込み、立ち上がった。
「待っててくれハニー。必ず迎えに行くから。そのときは…薔薇を受け取ってくれると嬉しいんだが」
言い逃げるように暖簾をくぐって出て行ってしまった男の残り香が鼻をかすめる。
暖簾から最後に見えた赤い耳が目に焼き付いて離れない。
それよりも真っ赤になっている自身の顔からは湯気が噴き出していた。急展開過ぎる。どうしよう。どうしよう!どうしよう!?
いたたまれなくて迎えを呼んで逃げ帰ってから何日経ったんだろう。
カラ松くんの前であんなに取り乱して何を口走ったのか記憶が定かじゃない。じわじわと悟ってはいたけれど、散々脈なしだと思っていたところへ刺激が強すぎてもしかして悪い夢だったんじゃないかとすら思う。
エレベーターの中で電源を落としたスマホはあれから一度も起動してない。いろんな人から連絡が来ているかと思うと怖くて再起動する勇気が持てなかった。置いて帰ってしまったトト子ちゃん、怒ってるだろうな…トッティも一松くんも多分私を連れ出すために来てくれていたんだよね、おそらくカラ松くんも…。差し出された真っ赤な薔薇越しに見た顔が忘れられない。ダズンローズ。それのもつ意味をちゃんとわかって私に差し出されていた。
『いや、名前はオレのこと本当に好きなんだなって』
バレた。ついにバレてしまった。
『なぁ、全然急なんかじゃない、オレは名前のことずっと…』
いや急でしょ!!!!!!!いや、急ではないか…?あんなことやこんなこともあったけど…いやいや、やっぱり急でしょ!!!!なんで!?いつから!?!?どういうこと!?!?!?!?
…なんてジタバタしていたら思いのほか時が経ち、久方ぶりに外に出てふらりと寄ったおでん屋でトト子ちゃんが語学留学に行ったこと、チョロ松くんが就職したこと、トド松くんが家を出たこと、そしてカラ松くんがチビ太家に居候して就活していることを聞いた。目白押しすぎる。もうこれ最終話近いじゃん。私が引きこもっている間にそんなことに…。
「なあ名前ちゃん。あいつ、すげー頑張っててさ。毎日夜中まで履歴書書いて朝早く出て行って…夜遅くに明るく帰ってくるんだけどよ、泣き腫らしたみてーに目の周り赤くしてて…もうオイラ見てらんねーんだ。一回会って慰めてやってくれよ」
「う…実は私、カラ松くんと喧嘩…ではないけど…ちょっといま気まずくて…」
「おーいチビ太~悪いが今日はここで食わしてくれない、か…」
元気よく暖簾をめくって入ってきた男とばっちり目が合う。そんなびっくりした顔する?びっくりしたのはこっちだっての。そっちは外から先客いるの見えてただろ。
見慣れない地味な色味のスーツに身を包んだ松野カラ松が暖簾を片手で押し上げたまま突っ立っていた。あ、とか、う、とか呻いて出ていこうとするカラ松の腕を強引に引っ張って私の隣に座らせた店主は「今日は早いじゃねーか」と言いながら大根とたまごの乗った皿を男の前に出し、帰れない雰囲気を作った。
「……」
「……」
「…なあ、そんな顔して座ってんのよしてくんねぇかな、オイラのおでんが不味いみたいじゃねーか」
わざと不機嫌そうにそう言ってくる店主に、慌てておでんを頬張り笑顔を見せる。だってチビ太くんのおでんは世界一おいしいもん。
おずおずとおでんに手をつけた隣の男に助け舟を出すように店主は明るく最近のカラ松がいかにすごいか、居候はしているけど飲食代は日雇いのバイトとかで稼いだ金で自炊してまかなっていること、おかげでちょっと瘦せたけどバイトと就活で毎日頑張っていてえらい、など面白おかしく説明してみせた。たしかに少し頬の丸みがシャープになっている気がする。
「ただよ~やっぱり男の一人暮らしの家にもうひとり成人男性が転がり込んでくるのは無理があるっていうかよ~…シンプルに狭いんだよな!(笑)ハタ坊んちと違って狭い安アパートだからさあ!」
意味ありげな目配せをしながらケラケラ笑うチビ太のアシストに耐えきれなくなった私は店主の意をくんで「うちくる?」とこぼした。
「…え?」
「うちっていうかハタ坊の家だけど…前にもしばらくいたでしょう?あの時と同じ暮らしなら提供できるし…あの時と違って私も貯金があるからハタ坊に頼らなくても何とかなるし…ハタ坊に言えば今より条件のいいバイトだって…」
「あまえたくない」
「えっ」
「申し出はありがたいが…オレだってもうあの時とは違う。あの時みたいに甘えたくないんだ。あの時名前に救ってもらって…ああ、女神って本当にいたんだって…名前はあの時からずっとオレの特別な存在で…」
「特別な…」
「ああ、そんな顔しないでくれ。たしかにあの時は”特別な親友”だって思ってた。でも今は…いや違うな、あの頃からずっと、出会ったその時からずっと変わらず、名前はオレの…大切なハニーなんだ」
やっとまともに目が合った隣の男はそう言ってはにかむように笑った。ずるい。そんな顔で、そんな声で、そんな大人っぽいスーツ姿で、そんな逃げ場のないこと、そんな勘違いしようのないことを、言うなんて。
「オレ、正社員になるから」
「えっ?」
「まずはバイトから…と思ったがそれで満足して甘えてしまいそうな自分が怖いんだ。実際、就活しながらバイトして…充分だと思ってしまいそうになる。でもそれじゃだめなんだ。それじゃ変われない…名前と釣り合う男になれない。どんな一軍が手を出してきたって引け目を感じないような、そんな正社員になるから…そしたら…つきあってほしい」
「…ど、どこへ」
「フッ、わかっているくせに小悪魔だな…。はっきり言う。オレの彼女になってほしい」
ず、ずるい!!!!!!そんな顔で(以下略)
目をそらせずに口をぱくぱくさせていると愛おしそうに目を細めたカラ松が皿の上の最後のひとかけらを口に放り込み、立ち上がった。
「待っててくれハニー。必ず迎えに行くから。そのときは…薔薇を受け取ってくれると嬉しいんだが」
言い逃げるように暖簾をくぐって出て行ってしまった男の残り香が鼻をかすめる。
暖簾から最後に見えた赤い耳が目に焼き付いて離れない。
それよりも真っ赤になっている自身の顔からは湯気が噴き出していた。急展開過ぎる。どうしよう。どうしよう!どうしよう!?