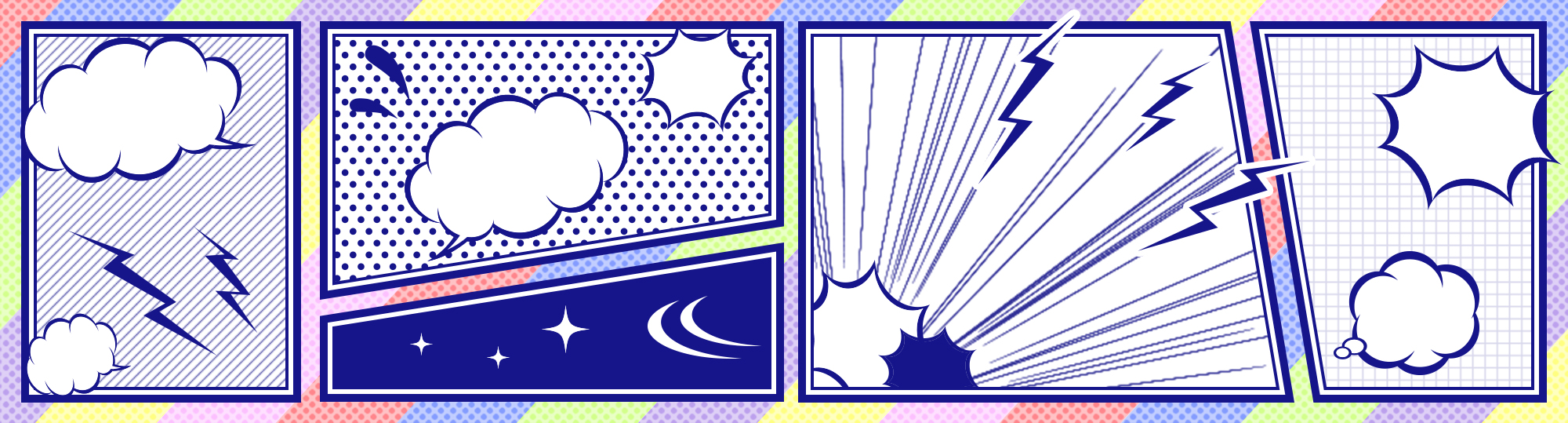短編
はじめにお名前変換してください
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「受け取りです」
「え、あれ、今日はハタ坊じゃねーの?」
淡いピンクとブルーが混ざり合う幻想的な空の下。
ようやくその役目を果たす時がきた赤提灯が輝きだす時間。
ちょうど肌寒くなって、ちょうど小腹もすいて、白くたゆたう温かな匂いに誘われ、ついつい寄ってしまいそうな小さな屋台。
その小さな城の小さな主が、自分よりさらに小さな幼馴染を待っていたというのに、現れたのは鼻を赤くして首をすぼめた少女だった。
「彼は飴とかおせんべいとか小さくて軽いもの専任になりました」
「…あー……」
先日の事案を思い出したチビ太は納得したように眉を下げて笑う。
「お鍋一つ、お願いします」
「名前ちゃんでも重いと思うけど大丈夫かあ?」
大きなカバンがいっぱいになるくらい負けじと大きな土鍋にたっぷり入ったあつあつのおでん。汁もなみなみ。絶対こぼすわけにはいかない。お客さんも困っちゃうし、背中全部やけどしたら私も困る。
しっかり蓋をして、カバンに固定して、さあ背負うぞ!と立ち上がろうとした。
「んっ……」
「…………」
「…………」
ひっくり返りはしなかったものの、カバンを背負ってしゃがんだまま立ち上がれない。びくともしない。えっ。チビ太くんこれ普通に持ち上げてカバンに入れてくれたけど、私持ち上げることすら出来ないの?たかが土鍋一個を?
己の非力さに絶望しながら膝に渾身の力を込めて、四つん這いになるくらい前のめりになってやっと立ち上がる。ふう。気を抜いたら後ろに倒れそう。
乗ってきた自転車に何とか跨って、それじゃあ、と振り向いたのがいけなかった。
「っあ、あ、わ、ああ、あ…!!!」
がくりと背後に振れる重心、浮く前輪、ああひっくり返る、と成すすべもなくハンドルを握りしめて目をぎゅっと瞑った私は、予想に反して後ろへぶっ倒れることはなかった。それどころか浮いた前輪は元通り地面につき、私の背中はふわりと軽くなった。
「…お~っと!も~危ないなぁ、亀じゃないんだから」
カバンごと私を支えて正しい位置に戻してくれたのは、屋台で早めの晩酌と洒落込んでいた赤いパーカー。
「ありがとう、おそ松くん」
「ん」
「もう大丈夫」
「いんや、大丈夫じゃないでしょ」
ほらね、と言いながら手を離される。
途端にぐらり、とまた後ろへ引っ張られ、しっかり掴んだハンドルのせいで前輪が浮き、自転車ごと尻もちをつきそうになる。
あわ、あ、わ、と情けない声を出して浮いた足をばたばたと地面につけようとする私を喉の奥で笑いながら、またカバンの底を支える形で助けてくれる。
「ほら、無理だって」
「で、でも、これをお届けしないと。前回すごく遅れてしまって、しかも商品が足りなくてクレームが入ったので今日こそは…」
「は~?同じ客かよ」
おそ松くんは、まったく、自分で食いに来いよな~とかなんとか言いながら、支えていたカバンを掴んで、私の両腕からするりと抜いてしまった。急に軽くなる背中。
「え、」
「うわ重っ!こりゃハタ坊にも名前ちゃんにも無理無理!三輪車も自転車も無理無理!」
「あ、で、でも、早く届けないと…!もう結構遅くなっちゃったし…前みたいに勝手に減らすわけにはいかないし…!」
「あーもう、仕方ないな~」
鼻の下をこすった彼は、屋台のわきに止めてあった水色のスクーターに跨った。
「チビ太~こいつ借りるわ」
「おう、ちゃんと返せよ!」
「わぁ~ってるって。ほら名前ちゃん、後ろ乗って」
ヘルメットを投げて寄こされて、慌てて自転車から降り、スクーターの後ろへ腰かける。
「急いでんでしょ?飛ばすからしっかり捕まってて」
「捕まるってどこへ」
「こーこ」
手の置き場に困っておろおろしていれば、遠慮なく手首を掴まれ、あっという間にしっかりと、何度も洗濯されてくたくたになった柔らかい赤の腰回りへまわされてしまった。顔に当たる布からほんのり柔軟剤と汗とたばこと出汁の匂いがする。あと少しだけお酒の匂いも。
「っ!?おそ松くん飲んでるじゃない!?」
「…あ。いや、だいじょーぶ、まだ飲んでない」
「あ、って言った!!」
「急いでるんでしょ~」
そう言うが早いか発進してしまったので、急なスピードにひるんで思わずぎゅっとしがみ付いてしまう。
前半身に伝わる熱が小刻みに震える。笑ってやがる。笑い事じゃないのに!
本当にまだ飲んでいないことを信じながら、頬をかすめる冷たい風を避けるように、目の前の赤に顔を埋めた。
マジックアワーに追いつけ、追い越せ、
(…で、こんなに待たせておいてミーのおでんはどこザンスか?)(えっ、おそ松くん荷物は)(あー…背中があったかかったから気付かなかったわ~おでんにしちゃあ柔らかいと思った~なはは!)(置いてきたの!?)(何しに来たザンスか!?シェー!!!!!)
「え、あれ、今日はハタ坊じゃねーの?」
淡いピンクとブルーが混ざり合う幻想的な空の下。
ようやくその役目を果たす時がきた赤提灯が輝きだす時間。
ちょうど肌寒くなって、ちょうど小腹もすいて、白くたゆたう温かな匂いに誘われ、ついつい寄ってしまいそうな小さな屋台。
その小さな城の小さな主が、自分よりさらに小さな幼馴染を待っていたというのに、現れたのは鼻を赤くして首をすぼめた少女だった。
「彼は飴とかおせんべいとか小さくて軽いもの専任になりました」
「…あー……」
先日の事案を思い出したチビ太は納得したように眉を下げて笑う。
「お鍋一つ、お願いします」
「名前ちゃんでも重いと思うけど大丈夫かあ?」
大きなカバンがいっぱいになるくらい負けじと大きな土鍋にたっぷり入ったあつあつのおでん。汁もなみなみ。絶対こぼすわけにはいかない。お客さんも困っちゃうし、背中全部やけどしたら私も困る。
しっかり蓋をして、カバンに固定して、さあ背負うぞ!と立ち上がろうとした。
「んっ……」
「…………」
「…………」
ひっくり返りはしなかったものの、カバンを背負ってしゃがんだまま立ち上がれない。びくともしない。えっ。チビ太くんこれ普通に持ち上げてカバンに入れてくれたけど、私持ち上げることすら出来ないの?たかが土鍋一個を?
己の非力さに絶望しながら膝に渾身の力を込めて、四つん這いになるくらい前のめりになってやっと立ち上がる。ふう。気を抜いたら後ろに倒れそう。
乗ってきた自転車に何とか跨って、それじゃあ、と振り向いたのがいけなかった。
「っあ、あ、わ、ああ、あ…!!!」
がくりと背後に振れる重心、浮く前輪、ああひっくり返る、と成すすべもなくハンドルを握りしめて目をぎゅっと瞑った私は、予想に反して後ろへぶっ倒れることはなかった。それどころか浮いた前輪は元通り地面につき、私の背中はふわりと軽くなった。
「…お~っと!も~危ないなぁ、亀じゃないんだから」
カバンごと私を支えて正しい位置に戻してくれたのは、屋台で早めの晩酌と洒落込んでいた赤いパーカー。
「ありがとう、おそ松くん」
「ん」
「もう大丈夫」
「いんや、大丈夫じゃないでしょ」
ほらね、と言いながら手を離される。
途端にぐらり、とまた後ろへ引っ張られ、しっかり掴んだハンドルのせいで前輪が浮き、自転車ごと尻もちをつきそうになる。
あわ、あ、わ、と情けない声を出して浮いた足をばたばたと地面につけようとする私を喉の奥で笑いながら、またカバンの底を支える形で助けてくれる。
「ほら、無理だって」
「で、でも、これをお届けしないと。前回すごく遅れてしまって、しかも商品が足りなくてクレームが入ったので今日こそは…」
「は~?同じ客かよ」
おそ松くんは、まったく、自分で食いに来いよな~とかなんとか言いながら、支えていたカバンを掴んで、私の両腕からするりと抜いてしまった。急に軽くなる背中。
「え、」
「うわ重っ!こりゃハタ坊にも名前ちゃんにも無理無理!三輪車も自転車も無理無理!」
「あ、で、でも、早く届けないと…!もう結構遅くなっちゃったし…前みたいに勝手に減らすわけにはいかないし…!」
「あーもう、仕方ないな~」
鼻の下をこすった彼は、屋台のわきに止めてあった水色のスクーターに跨った。
「チビ太~こいつ借りるわ」
「おう、ちゃんと返せよ!」
「わぁ~ってるって。ほら名前ちゃん、後ろ乗って」
ヘルメットを投げて寄こされて、慌てて自転車から降り、スクーターの後ろへ腰かける。
「急いでんでしょ?飛ばすからしっかり捕まってて」
「捕まるってどこへ」
「こーこ」
手の置き場に困っておろおろしていれば、遠慮なく手首を掴まれ、あっという間にしっかりと、何度も洗濯されてくたくたになった柔らかい赤の腰回りへまわされてしまった。顔に当たる布からほんのり柔軟剤と汗とたばこと出汁の匂いがする。あと少しだけお酒の匂いも。
「っ!?おそ松くん飲んでるじゃない!?」
「…あ。いや、だいじょーぶ、まだ飲んでない」
「あ、って言った!!」
「急いでるんでしょ~」
そう言うが早いか発進してしまったので、急なスピードにひるんで思わずぎゅっとしがみ付いてしまう。
前半身に伝わる熱が小刻みに震える。笑ってやがる。笑い事じゃないのに!
本当にまだ飲んでいないことを信じながら、頬をかすめる冷たい風を避けるように、目の前の赤に顔を埋めた。
マジックアワーに追いつけ、追い越せ、
(…で、こんなに待たせておいてミーのおでんはどこザンスか?)(えっ、おそ松くん荷物は)(あー…背中があったかかったから気付かなかったわ~おでんにしちゃあ柔らかいと思った~なはは!)(置いてきたの!?)(何しに来たザンスか!?シェー!!!!!)